『今昔物語』山野楽器スタッフ編 関秀能(Sax)
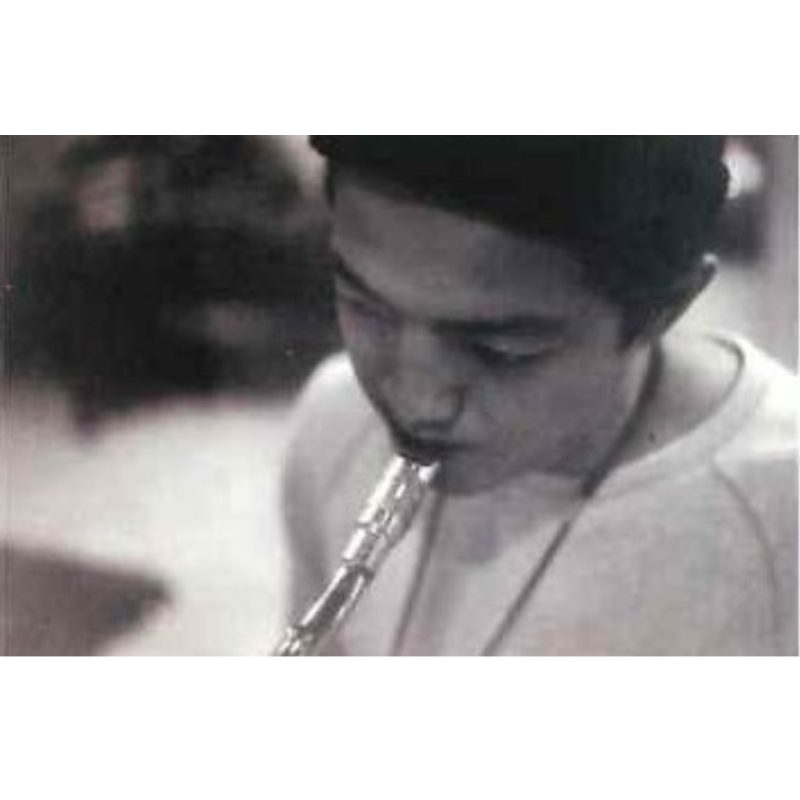
■東洋大学 グルービー・サウンズ・ジャズ・オーケストラ
1994年 第25回大会出場
※2007年7月、山野楽器社内の冊子に寄稿された文章を当時のまま掲載しています。(現在、ウインドクルー勤務) 高校まで運動部に所属する中で、私がJAZZを聴くようになったのは、友達がサッチモのCDを貸してくれた中学生の頃からでした。その後、マイルス、コルトレーンなどの名盤を図書館に行っては借り漁り、カセットテープに録音しては楽しんでいました。 大学に進学しBIG BAND部なるものに入部したのは2年に進級してからです。1年の時はひとりで勝手に大学生活に失望し、ぶらぶらしていました。そんな中、何か大学生活の証を残したいと思い始め、楽器を演奏できるようになりたい、どうせならばJAZZをやりたいとの思いでBIG BAND部の門を叩きました。そこで初めて【YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST】を知ったのです。楽器初心者の私がまだマウスピースだけでリードをうまく振動させる練習をしている横で、先輩たちが必死になって「ヤマノ」に対し取り組んでいた姿をよく覚えています。煮詰まっては前進、また煮詰まっては前進という事を何回も繰り返しており、非常に近寄りがたいオーラを感じたものです。 うちのバンドは「ヤマノ」が終わると代替わりします。私はその年、マネージャーになり、93年の第24回大会は出場メンバーになれなかったものの、そのマネージャーという立場で臨みました。
本店(別ビルの事務所だったかも…?)でマネージャー会議に数回参加したことを覚えています。会議は非常に紳士的な雰囲気で、同時に山野楽器が学生BIG BANDを積極的に支援していることが私に伝わってきました。私はそんな山野楽器っていいなぁと思い、入社を志望するきっかけとなったのでした。 この大会が終わり私はバンドマスターになりました。学生BIG BANDの多くは、バンドマスター(バンマス)とコンサートマスター(コンマス)というポジションがあります。大ざっぱに言うとコンマスはバンドの技術面を仕切る立場で、バンマスは言わば部長です。他の部員より比較的お酒が強かったからでしょうか、そういう立場になりました。 それからは大変でした。新入生が入ってきたときは総勢約100人の大所帯となり、部をまとめるのに苦労しました。何せ楽器の技術では皆を引っ張っていけなかったものですから、ただ一生懸命やるだけだったのです。 94年の第25回大会で私はついに「ヤマノ」のステージに立ちました。
でも、当日のステージ上の事はほとんど覚えていません。その前の練習で自分たちを追い込んだ日々の記憶しかないんです。苦労を分かち合ったメンバーとのその日の打ち上げは大いに盛り上がりました。私が在籍した3年間、賞とは全く無縁でしたが、その時のベストは尽くせた気がします。学生時代に一番時間をかけた大切なもの、その中で最も真剣に挑んだもの、それが「ヤマノ」でした。 話は変わりますが、私は入社し数年を経て大阪営業所に異動、10年間営業を務めました。西日本でも「ヤマノ」は私の予想以上に広く知れ渡っていました。学生BIG BAND出身で「ヤマノ」のOBが各地の社会人BIG BANDなどで活躍されています。また音楽普及イベントで検討・模索している取引先からも手本となるプランとして受け止められており、多くの質問を受けました。 私はこのイベントを誇りに思っています。今後もずっと開催できるよう、何か役に立つ事があれば、微力ながら協力を惜しみません。一生懸命音楽に取り組んでいる人をずっと応援していきたいと思います。
